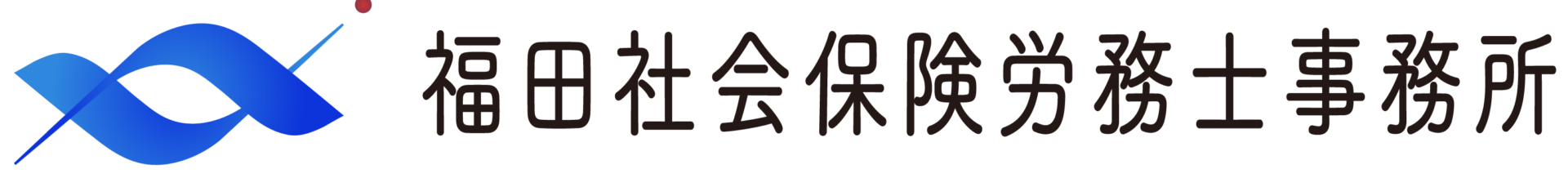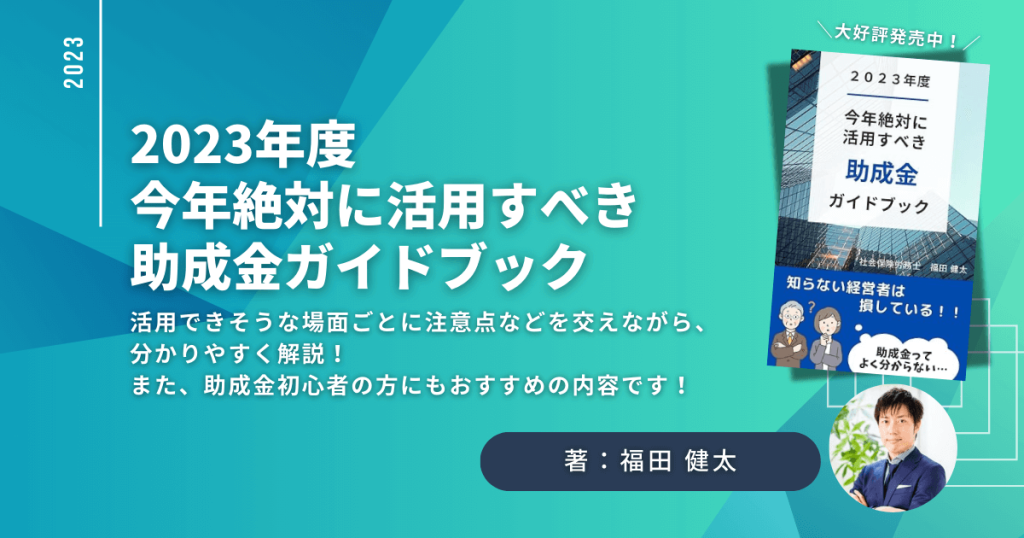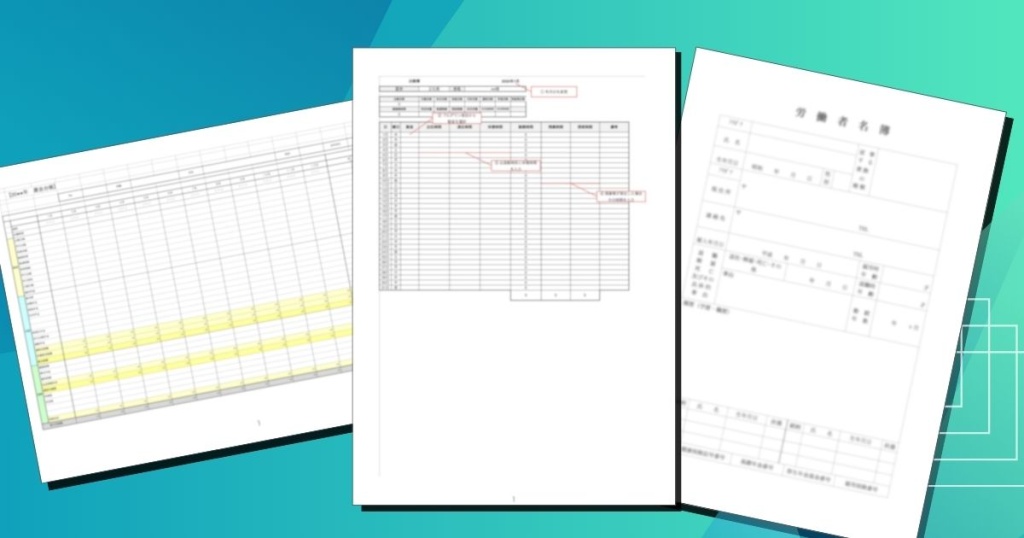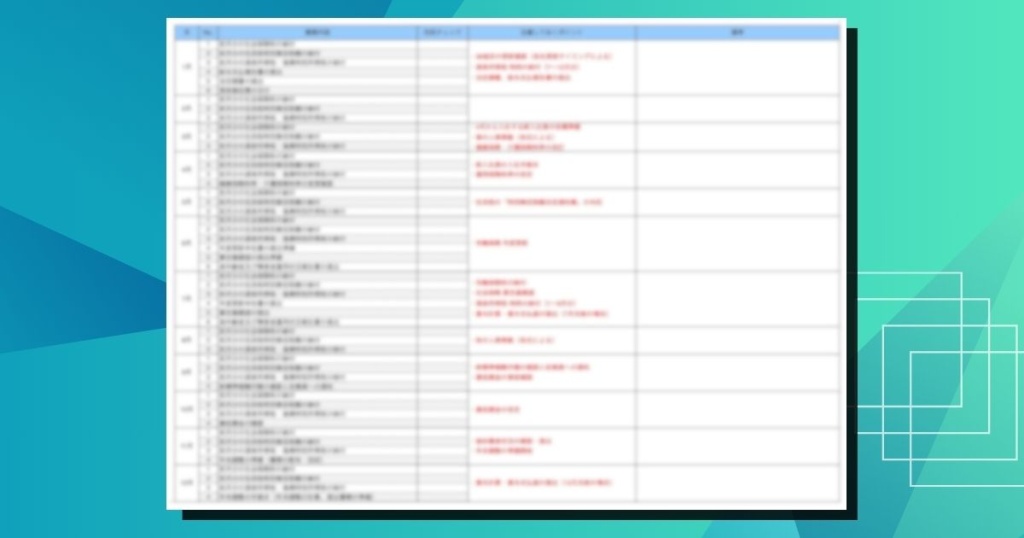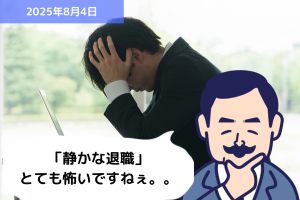静かな退職という言葉を知っていますか??
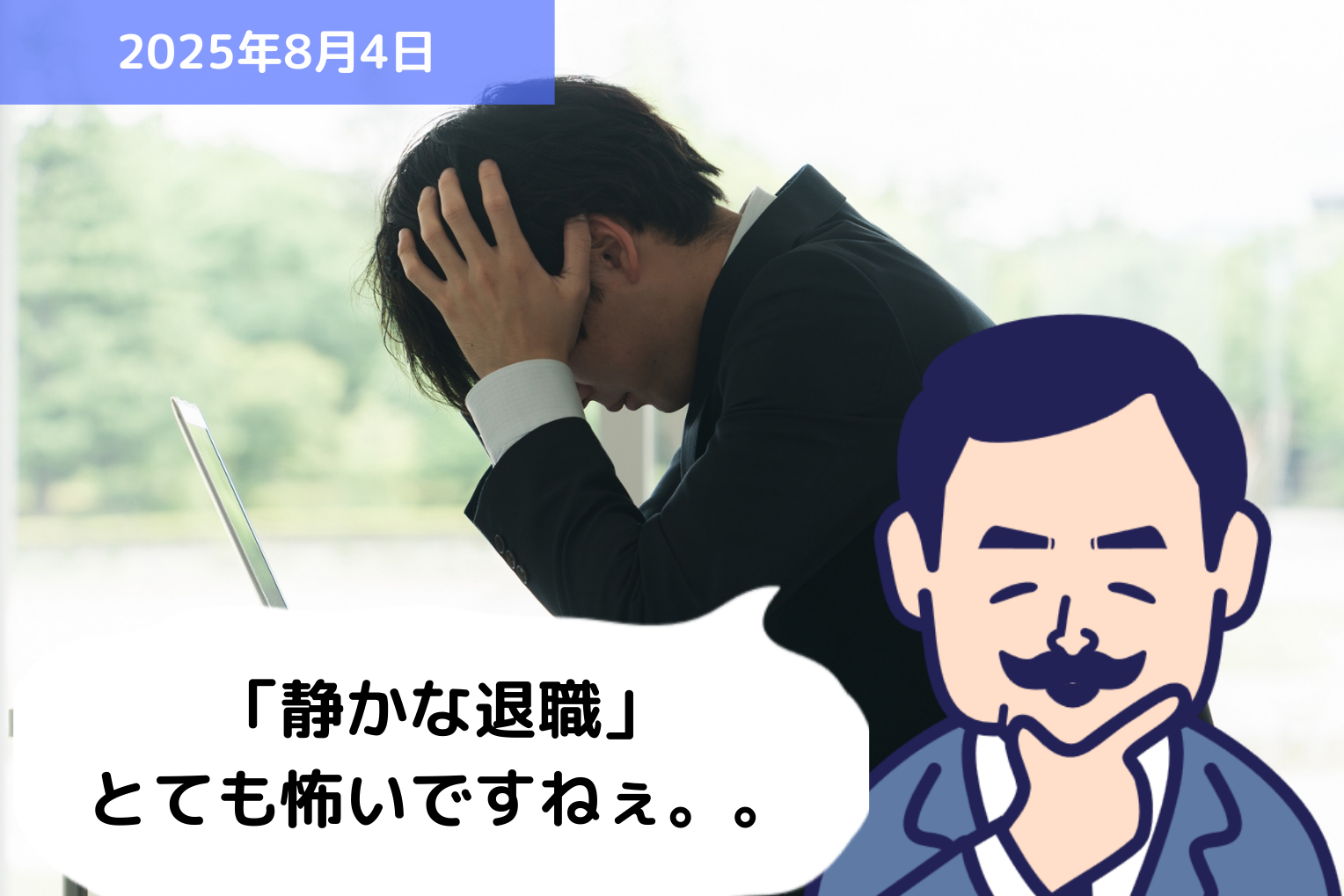
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、昨今話題になっている「静かな退職」という言葉についてお伝えします!
 製造業 Y社長
製造業 Y社長一度耳にしたことが
ある気はしますが。。
 社労士 福田
社労士 福田SNSを中心に話題に
なっている単語ですね。
一緒に考えていきましょう!
「静かな退職」とは?
「静かな退職(quiet quitting)」とは、やりがいやキャリアアップは求めずに、必要最低限の仕事を淡々とこなすこと。
近年のワークライフバランスを重視する動きが加速化したことによって、この働き方が増え、アメリカを中心に注目されています。
ある調査では正社員の4割以上が「静かな退職」をしている現状であり、もはや一般的になりつつある状況です。
コロナの影響によりリモートワークが増加しワークライフバランスへの感度が高まったことや、Z世代の社会進出が進み新しい感性の働き手が増えたことからホットになっているキーワードです。
最近のワークライフバランスの考え方については下記の過去記事をご覧ください。

「静かな退職」に対する意見
会社の役に立っていないなどという否定的な意見が多い中で、肯定的な側面もあることも知っておいて理解を深めていきたいところです。
・他従業員に消極的な姿勢が伝播する
・スキルアップを目的にしていないと会社の成長が見込めず不利益を被る
・同僚とのコミュニケーションを避けることで、社内の人間関係に問題が起きる
・プライベートの時間を守るために時間内に終わらせられるよう効率的に業務を進める意識が高まる
・過度な労働から距離を置くことで心身の健康を保つことができる
・そういった働き方の人のほうが向いている業務があるので、人事配置次第の問題
世代の特性による労働への向き合い方であれば尊重したい考えですが、考えられる問題点としては環境の不一致や評価・処遇への不満、仕事環境などが要因で、不本意ながらこういった状況になっている人がいることです。
評価や環境の不満によって、このような状態に陥っているのであれば早急に解消が必要です。
社員のモチベーションにかかわる取り組みについて詳しく知りたい方は過去記事をぜひご参照ください。
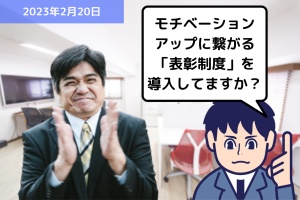
または、上記の理由ではなく元々安定志向で与えられた範囲の仕事をコツコツとこなすことこそが得意な性格の人もいます。
「静かな退職」のような態度の社員だ、と距離を置いた評価をするのではなく、社員の特性を見極め適切な人事配置をすることでむしろ効率化に寄与する可能性があることも考慮しておきたいですね!
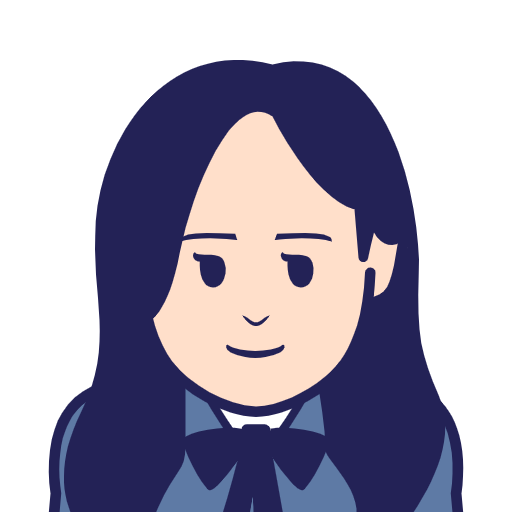 スタッフ 奥田
スタッフ 奥田労務手続きに関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!