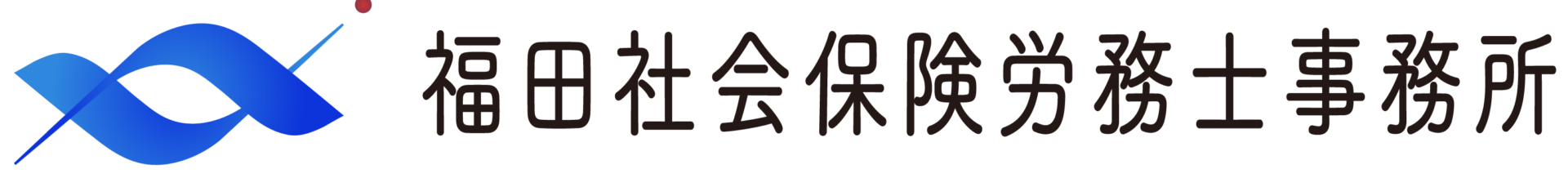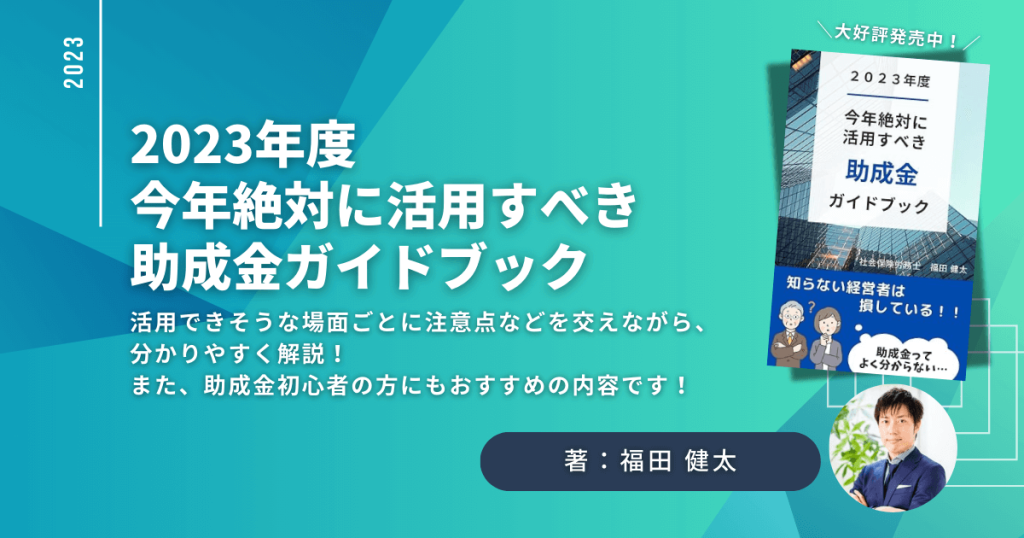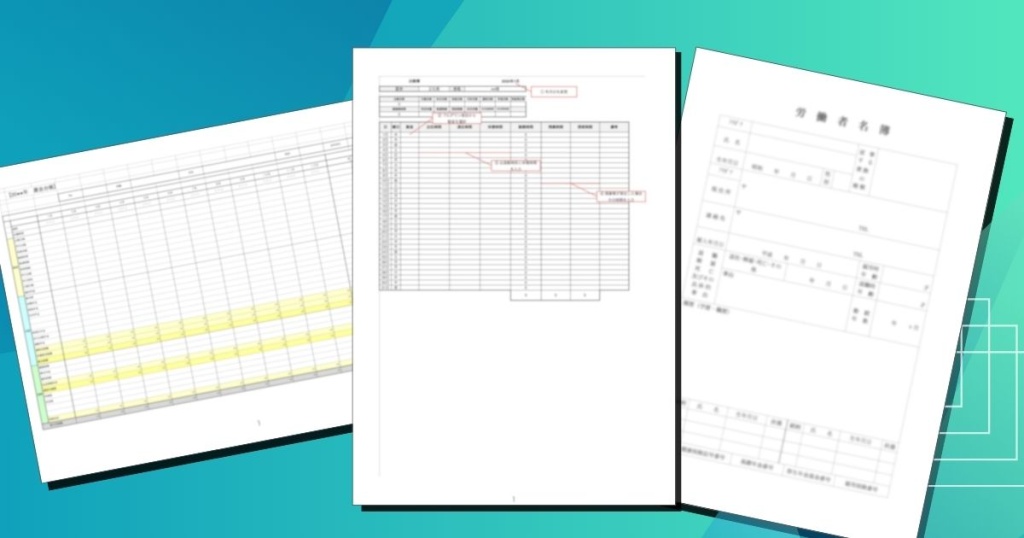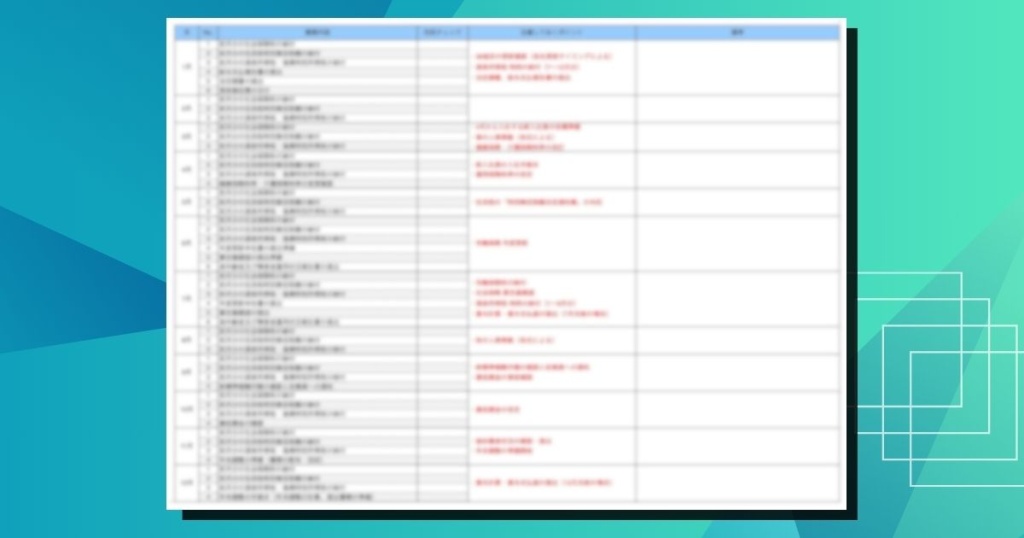ハラスメント講座 Part①

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、今年の4月から適用範囲が拡大になったパワハラ防止法など、ここ数年なにかと話題が多いハラスメントについて、全2回に分けてお話したいと思います。
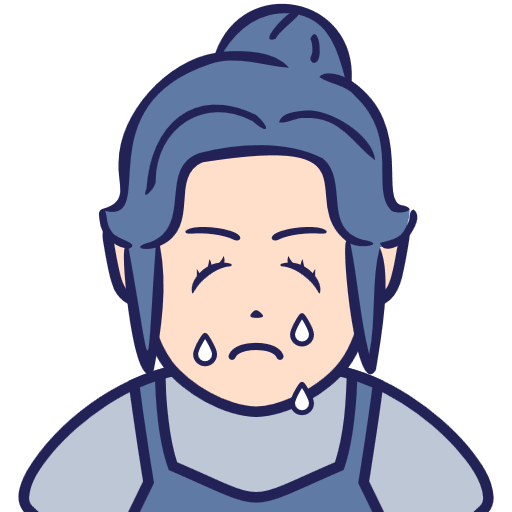 スーパー勤務 Y美
スーパー勤務 Y美私もセクハラされた経験が
あります。。
とても辛かったですー。。
 社労士 福田
社労士 福田そうでしたか、それは大変辛い
経験をなさいましたねぇ。。
ハラスメントと言えば、セクハラが代表格ですが、典型的な例としてこちらの4種類があります。
① セクハラ(セクシュアルハラスメント)
性的な言動や行動によって不利益を受けたり、就業環境が害されたりするハラスメント。
② パワハラ(パワーハラスメント)
職場での上下関係や権力を利用して、嫌がらせ行為を行うハラスメント。
③ マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠や出産、子育てを理由として、嫌がらせや不利益な取り扱いを行うハラスメント。
④ アルハラ(アルコールハラスメント)
会社の飲み会の席で、上司が拒否できない状況で飲酒を強要する等のハラスメント。
こういったハラスメントですが、身近に行われていない方も多くいらっしゃるかもしれません。
ですが、「いじめ・嫌がらせ」に関する労働相談が、2021年度は約11万件と非常に多いのです!
しかも、2012年以降、様々な労働相談の項目がある中で、10年連続で最多項目となっていることからも、いかにハラスメントに関する問題が多いのかが伺えます。
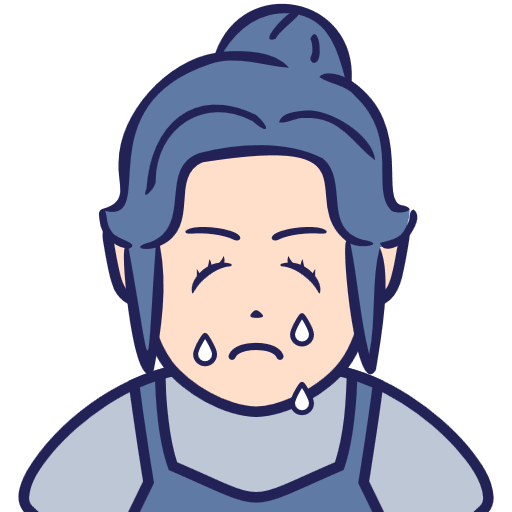 スーパー勤務 Y美
スーパー勤務 Y美そんなに多いんですか~!
私と同じように、多くの方が
辛い思いをされてるかと思うと
とても悲しいです。。
 社労士 福田
社労士 福田私も同じ気持ちです。
少しでも働きやすい職場が
増えてほしいです!
では、このようなハラスメントは何故起こってしまうのでしょうか。
そこには大きく分けて、2つの原因があります。
① 個人に起因する要因
ハラスメントをしてしまう人自身が、してはいけないことを正しく知らなかったり、自分の行為がハラスメントに該当することに気づいていないといった場合があります。
このようなことが行らないように、会社側から従業員に対してハラスメントに関する正しい知識を指導していくことが重要になります。
② 組織に起因する要因
ハラスメントが起こりやすい組織として、日常的に強いストレスがあったり、閉鎖的な組織体質であるといったことが挙げられます。
例えば、強いストレスの捌け口としてハラスメントをしてしまう人が現れたり、閉鎖的であるからハラスメントが行われていても問題視されないといったような場合があるのです。
こちらも会社の組織体質を変えていくことで、ハラスメントが起こりづらい職場環境に変化させていくことができます。
 スーパー勤務 Y美
スーパー勤務 Y美確かに私が居た職場も、
とても閉鎖的で誰にも
相談できないし、研修とか
教育とかも全然されて
いませんでした。
 社労士 福田
社労士 福田会社の取り組み方を変える
だけで、Y美さんのような
辛い思いをされる人が減るの
なら、やるしかないですよね!
では、もしハラスメントが起こってしまったらどうなるのでしょうか?
ハラスメントとして認定された場合、「不法行為」にあたり、民法709条により加害者は被害者に対して、慰謝料などの損害賠償責任を負うことになります。
また、場合によっては、民事事件に留まらず刑事事件にまで発展することもあります。
では、罰せられるのは加害者だけなのでしょうか?
実は会社にも、被害者に対して損害賠償責任を負わなければならなくなる場合があるのです。
会社には、従業員が生命や身体等の安全を確保して労働ができるよう、必要な配慮をしなければならいという「安全配慮義務」というものが課されています。
この「安全配慮義務」を怠ったためにハラスメントが起こってしまったということで、会社側にも法的責任が問われるのです。
ですので、ハラスメントが起こらないような職場環境を作るためにも、例えばこちらのような取り組みをされてみてはいかがでしょうか?
・従業員に対して、ハラスメントに関する研修を実施。
・ハラスメントを防ぐための、会社からの定期的な情報発信。
・予防や早期解決に繋げるため、相談窓口の設置。
・ハラスメントが行われた場合の懲戒等の罰則を規定。
 スタッフ M子
スタッフ M子当事務所では、就業規則の
作成や労務相談も行って
おります。お気軽に
ご相談くださいね!
明日は、今年適用範囲が拡大となった、パワハラについて詳しく解説したいと思います。